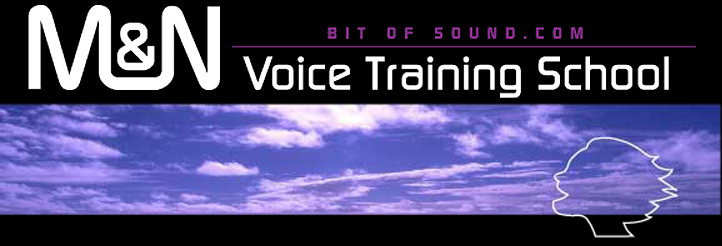こんにちは。
東京・吉祥寺 M&N Bit Of Sound ボイストレーニングスクール ボイストレーナーのけいこです。
今回は、ミュージカルの発声について、分かりやすく、ポピュラーなミュージカル映画等も例に挙げながら、私の主観でお話ししてみたいと思います。
ミュージカルの発声には、大きく分けて、クラシック系と、ポップス系の両方があります。これは、演目によって違うようです。
古い時代のミュージカルは、比較的クラシック系の発声が必要とされる場合があります。具体的に演目を挙げてみます。「南太平洋」、「サウンド オブ ミュージック」、サラ ブライトマンの為に書かれた「オペラ座の怪人」、役柄にもよりますが、「ウエスト サイド ストーリー」、「美女と野獣」等。
「レ ミゼラブル」に関しては、エポニーヌ役はポップス系だけど、フォンティーヌ役は、どちらもあるそうで、これは演出家次第だと、聞いたことがあります。何れも、クラシックの要素があった方がいい演目で、基本的には、圧倒的にポップス系の発声が必要だと思います。例を挙げてみます。「シカゴ」、「レント」、「コーラスライン」、「ライオン キング」、「アラジン」、最近のミュージカル映画、「ラ ラ ランド」、「グレイテスト ショウマン」等。「ジーザスクライストスーパースター」。この演目は、舞台には出演されていませんが、オリジナルの録音は、ディープパープルのヴォーカリスト、イアン ギランが参加しています。
他にも沢山のミュージカルがありますが、演目によって、役柄によって発声の仕方が違うこと。そして、演出家によっても、どちらを求められるかわかりませんが、圧倒的にポップス系の発声が求められています。クラシック系と、ポップス系の発声を使い分けること、そのコントロールはできますが、喉(声帯)への負担は大きいです。以前の講座、リヒロ先生の「クラシックとポップスの違い」も参考にしてみてください。
ミュージカル俳優を目指している方からよくある質問の一つとして、ポップス曲をかっこよく歌えない。という悩み。私が思うに、言葉を話すように歌う(言葉のリズムを大切にする)ことは、大事なことですが、意識し過ぎて口先だけで歌っているような、ポップスを歌うのに大事な、グルーブ感がなくなりがちです。そして表現しようと、演じようとしてしまうのか、無駄な感情が入り、声帯の位置がずれてしまいます。ミュージカル俳優だけでなく、世界のスーパーボーカリスト達の歌を沢山聞いて、見て、吸収してください。それから、ブロードウェイ、ウエストエンドのパフォーマンスを参考にしてみてはどうでしょうか。オリジナルキャストのパフォーマンスは必見です。
最後に、ミュージカルは、演出家の要望に応えられることが大事です。その為に、M&N Bit Of Soundでの基本的なボイストレーニングが必要になってきますので、信じて、今日もよいボイトレができたら幸いです。私達も、サポート頑張ります。